cero『Obscure Ride』(Rough)
予めメモしたアルバム発売日にタワーレコードへと足を運び、初回限定版がまだ残っていることに心から安堵してレジに向かい、帰り道にどうしても気になって歌詞カードを取り出し、部屋に戻ると急かされるようにCDをセットし、ほんのちょっとの不安を抱えながらスタートボタンを押す。僕が最後にそんな甘酸っぱい経験をしたのはいつだっけ?この国のポップミュージックの新たなメルクマール、『Obscure Ride』以前に。
Obscure Ride/cero 2015

(アルバムの詳細、特にストーリーの読解については次の「ディティール編」に譲るとして、この「ラフ編」では総論として極めて私的なアプローチを試みる。)
ロバート・グラスパー、ディアンジェロといった所謂ネオソウルや「ニューチャプター」なジャズの流れを汲んだ、彼らなりの最突端のブラック・ミュージックへのアプローチが身を結んだサウンドの素晴らしさは既に多くの人達が指摘し賞賛しているので、今更そこに僕が語れるようなことはあまり残っていないのだけど、やはり余計な軽口を叩かずにはいられない。Comtemporary Exotica Rock Orchestra、改め、Comtemporary ”Eclectic” Repllica Orchestra、と名乗る彼らのサウンドと小沢健二という奇妙なミュージシャンの、その中でもひときわ奇妙な『eclectic』という作品との関係について。
Eclectic/小沢健二 2002
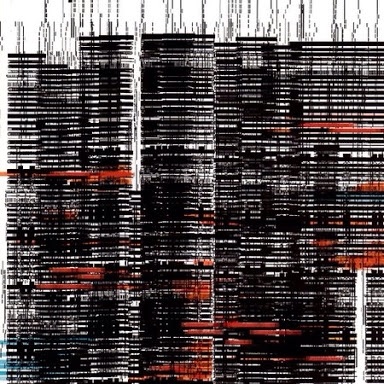
「あんたさあ、よくceroとオザケンとフィッシュマンズを比較して話してるけど、一緒にしないでほしいんだよね」と酔っ払った女友達から電話がかかってきて、僕はムカついてそこでガチャンと電話を切ってしまったのだけど、彼女の怒りもきっと正当なもので、個人的なバイアス抜きにceroの音楽からオザケン(≠小沢健二)とフィッシュマンズに強い繋がりを見出すのは確かに難しい。だから、これから僕が言わんとする「『Obscure Ride』が90年代を完全に終わらせた」なんて戯言は、この何年かあらゆるジャンルで行われてきたのだろう90年代の残党狩りの最もミニマルでパーソナルなものの一つに過ぎない。そして僕にとって90年代の象徴がその2組のミュージシャンだった、というそれだけの話。
グルーヴは黒いのに、決してブラック・ミュージックにはなれない/ならない、という感覚。それをコンプレックスではなくて”Repllica”であると鷹揚に宣言するceroの感覚は僕にはとてもしっくりとくる。どぎつい性愛を剥き出しにしたり、レベルミュージックとしてパワフルになり過ぎることなく、しかし敬虔さと神秘性を拝借したあくまで「借り物」のスムースなプラスティック・ソウル。つまりは小沢健二『Eclectic』をceroなりに解釈し、アップデートしたのが『Obscure Ride』のサウンドであるという見立ては決して的外れなものではないだろう。
しかし『Eclectic』と『Obscure Ride』には決定的に異なる点がある。性について歌うか、歌わないか(もしくは歌えるか/歌えないか)。『Obscure Ride』について絶賛しつつ「タナトスはあるがエロスがない」と評したライターの宇野惟正氏が行ったインタビューで、ceroの中心人物である高城晶平はこんな事を語っている。
あの『Eclectic』というすごく冷たい質感をもったエロティックで孤独なアルバムを、人の世に下ろしてあげたいなっていう、ちょっと勝手な思い込みがあって(笑)。僕らみたいな普通の兄ちゃんたちが気さくに演奏してみたら、ちょっとはあのアルバムに違う方向から光を当てることができるんじゃないかなって。
ceroがこれまで作ってきた作品の流れで、そういう性的なものを突然入れ込むっていうのは、なかなか苦戦したところで(笑)
『Eclectic』という存在が高く天上にあるものだとは僕は思わない。あのアルバムに何らかの「高さ」があるとすれば、それは子供が大人に追いつこうとする背伸びによって生じたものではないだろうか。勿論その「背伸び」にはNYでの同時多発テロという精神的な割礼を受けた後の痛々しさや切実さも伴っていたが、性に目覚めたばかりのマセガキのように、作中で執拗にセックスについて歌う彼の姿は微笑ましくすらある。(特に『Eclectic』に先駆けて発表された「Got to Give it Up」の日本語カバーのダサさは衝撃的だった。)
奇しくも2015年にDCPRG改めdCprGを再始動させ、一層「本物の」ブラック・ミュージックへの接近をみせた菊地成孔というミュージシャンがいる。「大人が大人になれないでいることを社会的に許しちゃうのは、子供に対する虐待だ」と断罪し、「大人であること」に拘泥する彼は『Eclectic』についてこう評している。
すげえ好き。とにかく、ここまで大人という記号をちりばめながら七五三のスーツみたいにしか聴こえない。という点が先ず天才的。
『Eclectic』が「オトナごっこのコドモ」の音楽だとして、では『Obscure Ride』はどうだろうか?菊地成孔からすればどちらも同じ「オトナごっこのコドモ」だろうが、僕はceroに小沢健二が成し遂げれなかった「成熟」を果たしているように感じられた。気心しれた多くのゲストを招集した演奏はどこまでも開放的であり、シリアスな楽曲であっても室内楽的な閉塞感とは皆無だ。「引きこもり」からコミットへの成熟。ことさらエロスや自意識に頼ることなく、豊かで複雑なストーリーを駆使した語り口にも余裕が感じられる。小沢健二やフィッシュマンズがBGMとなった岡崎京子やよしもとよしともの漫画の登場人物たち(または碇シンジ)が孕んでいた欠落や虚無をデストルドーにまで育むことなく、異なる形で昇華するという成熟とも取れる。(余談だが、ではceroがBGMとなる漫画は一体何かとなると、僕が知る限りでは田島列島とかピッタリな気がする。)
オザケン時代の小沢健二、つまり『犬は吠えるがキャラバンは進む』〜『LIFE』〜『球体の奏でる音楽』〜「ある光」までの彼の活動は彼なりの「大人」のロールモデルを提示していたのだと僕は思っている。彼の王子様キャラはガールズに向けてじゃなく、間違いなくボーイズに向けられたものだった。男の子のケツを思いっきり蹴り上げ、「いつも思いっきり伝えてなくちゃ」と啓蒙するマッチョイズムとは無縁の兄貴分としての「オザケン」は、やはりすぐに頓挫し、成熟と老成を同時に獲得しようとした『球体の奏でる音楽』とヒップホップに接近したアルバム未収録のシングル群を経て、敗北宣言ともとれる「ある光」へと至ることになる。この曲における「線路」が何のメタファーであるかについては意見が分かれるだろうが、僕は「成熟=大人になる」事の比喩だと考える。そして、彼は明らかにそこから降りようとしている。「Let's get on the board!」と乗り込むのは「飛行機」だ。(同時多発テロで使用されたのも飛行機=1000灯機である、というのは我ながらあまりに妄想が過ぎる。)つまり線路を離れ空を飛ぶ=成熟という物語から自由になるという、ある種の退行と開き直りを置き手紙として彼はNYへと雲隠れし、ちゃっかりと大人になるまで僕らの前から完全にその姿を消した。
結果はどうあれ成熟を目指した小沢健二に対し、最初から成熟することを放棄したのがフィッシュマンズというバンドであった、という話はさすがに脱線が過ぎるのでここでは割愛するが、「スマイル」での「100ミリちょっとの」の引用を例に出すまでもなく、ceroに大きく影響を与えたバンドのひとつには違いない。しかし先にも書いたように、『Obscure Ride』のサウンドにその影響を見出すのは難しい。(しかし「夜去」の「とびきり素敵なテントを張ろうよ」というフレーズは単に偶然だろうか?)フィッシュマンズとceroの比較には「ナイトクルージング」と「大停電の夜に」まで遡ろう。
窓はあけておくんだ
いい声聞こえそうさ(ナイトクルージング)
大停電の夜に
僕は手紙書く手をとめ
窓を開けて目を閉じ
街のざわざわに聞き入る
外には夜汽車が走っていた
手を振る友達楽しそう
普通の会話を愛している
手を振る友達淋しそう(大停電の夜に)
「ナイトクルージング」の登場人物は主人公以外には「あの娘」だけだ。ならば聞こえてくる「いい声」の主体は「あの娘」だろうか?そんな事はない。その声を発するのは広く「他者」であり、佐藤伸治の表現を借りるなら「新しい人」たちの声だ。
ホラ こんなに伝えたいのにねえ
新しい人 格好悪い人
呼んで 呼んで 呼んでよやさしい人 みっともない人
呼んで 呼んで 呼んでよ(新しい人)
小沢健二の「世界に向かってハローなんつって手を振る」という積極的(すぎる)な対峙ではなく、「窓を開ける」という慎ましやかな世界との距離感はしかし、ラストアルバムとなった『宇宙日本世田谷』において結局は「2人だけで夕陽を眺める」という死の香りが漂う閉鎖された景色へと収束されてしまう。
ceroの描く夜では窓を開けても「いい声」が聞こえてくることなく、ただ街のざわめきだけが鳴っている。登場人物は僕と君と友達と、大停電の街に住んでいる多くの人達。ここでは世界と対峙する/しない以前に最初から繋がっている/しまっている。僕は自ら窓を開けて、君は懐中電灯で闇を照らし、冷たい風を介して緩やかに接続される。その事が類似した題材を扱った「ナイトクルージング」と「大停電の夜に」のテクスチャーを決定的に異なるものにしている。
(僕が思う)小沢健二/フィッシュマンズからceroへの流れというのは、村上春樹が言うところの「デタッチメントからコミットメント」の潮流のひとつであり、それは振り子のようなもので成熟とは程遠いものであったとしても、僕はceroに90年代の更新を見出さずにはいられない。繰り返すが、きっとceroにそんな意図はないし、もちろん小沢健二とフィッシュマンズの音楽もそんな簡単に乗り越えられてしまうヤワなもんじゃ決してない。僕の中にいる彼らの暗殺を勝手にceroに託しただけに過ぎない。そして『Obscure Ride』は容易くそのミッションを遂行してくれた。少し寂しくなるほどに。
僕は憧れ、羨んでいた。無邪気に美しい終末を夢想できた、終わりなき日常を。平坦な戦場に潜む、熱いナイフのように尖るものを。ふたりぼっちの世界で「死ぬほど楽しい毎日なんてまっぴらゴメンだよ」と吐き捨てることを。コミットメントなんてクソ喰らえって思っていたし、成熟なんて概念に思いっきり中指を立てて、唾を吐きかけている。
でも、そんなのは子供の時の話さ。
フィッシュマンズが世界最高のバンドだと思っていた15歳の僕に、小沢健二が世界最高のミュージシャンだと思っていた19歳の僕に、時空を越えた電話をかけよう。
「よお、残念だったな、フィッシュマンズよりも素晴らしいサウンドで小沢健二よりも素晴らしい歌詞を書くバンドが現れるんだ、名前は…」
きっと僕はムカついてそこでガチャンと電話を切るだろう。


